2019年度年次報告書より
Report of India
清水 友美Tomomi Shimizu
インド事業部ディレクター
朝、家の近くにある大きな公園で、木にもたれかかりながらこの8年を思い返していた。私がかものはしと出会ってから丸8年。大きな木を見あげ、土からせり出す根を大量の蟻が行き来しているのをみていたら、気付いたら涙が止まらなかった。
2020年3月末からインドで全土封鎖が始まり、日雇い労働者は仕事を失い、収入を絶たれた。私たちが一緒に活動するサバイバーリーダーたちもその影響を免れず、本当に餓死者が出るのではないかと私は不安になり、緊急調査をして現金支給を決めた。5月に入って今度は大型サイクロンが西ベンガル州を襲い、特に南24区に壊滅的なダメージを与えた。かもインドチームの多くも被災し、ライフライン復旧までに相当の時間を要した。私は、遠い東京で何もできず、ただただ不安な毎日を過ごした。ダブル災害で連絡が取れなくなったサバイバーリーダーたちのあまりの多さに、今度こそ死者がいるかもしれないと覚悟を決めつつ、普段はレジリエンス(回復力)の高いパートナーたちが今回ばかりは無力感に打ちひしがれているのを見て、私はさらに落ち込んだ。その合間に、生きていくのがしんどくなったと連絡をくれた人たちがいて、そのとき持ち合わせていた自分のすべてのエネルギーで彼女たちと向き合った。
それでも人は強いもので、皆で支え合い、たくさんの苦労はあるけれど、今のところ一人も死者を出さず、なんとか前に歩を進めてきた。だから今、切迫した大きな悲しみがあるわけではないが、止まらない涙をみたときに、8年かけて、意識的にも無意識的にも多くの人の悲しみや怒り、やるせなさを自分の中に吸収してきた、その浄化作用としての涙なのだろうなと思った。
この8年を振り返るとき、なぜ私はかものはしで人身売買の問題に関わっているのか、私の人生の中でどんな意味があるのか、インドの人身売買問題にとって、私が関わってきたことにもし意味があるのだとすれば、どんな意味があるのか、ということが中心にくる。
「人身売買問題」を
取り扱う
私はこれまでの21年のキャリアの中で、サラワク先住民族の土地権利回復運動や、アジアの都市化問題、スマトラ沖大地震後のアチェでの復興支援、スリランカの内戦復興支援に関わってきた。多くの社会課題がある中で、割と「闘い」がテーマの分野で働いてきたと思う。でも、この反人身売買セクターは、私がこれまで見てきたどの分野とも大きく異なる。ここは、圧倒的に多くの、「痛み」「哀しみ」「怒り」が渦巻いている。人が人を売るという行為、他者に自己を侵害されるという体験、信じていた人に裏切られるという経験。あたかも人類のそういう悲しみがぎゅっと凝縮しているかのような、濃度の高い悲しみがこのセクターには存在している。
反人身売買セクターでは横の連携がきわめて弱い。それは、あまりにもこの問題が大きく、痛みが強すぎて、自分にいったい何ができるのだろうかという無力感を、どんな立場であれ関わっている多くの人が感じ、結果それが他者と効果的に、前向きに関わることを阻んでいるのではないかと思っている。
私もまた、たくさんの痛みと悲しみをもろに受けとってきたのだなということを、木を見ながら、蟻を見ながら思った。助けられなかった命、昔背負った傷を今もなお生きている人たち、私にとってとても大切な人たち。その人たちの笑顔を奪ったviolence。

©Siddhartha Hajra
パラダイムシフト
昔の私だと、「ゆるせない。だからこそ、加害者を逮捕することでこの問題をなくすんだ!」と考え、少なくとも6年間はそうやって走ってきた。しかし、このところのインド事業は「怒りを転化してそれを起爆剤として解決を見出す」というよりも、起きてしまったことは起きてしまったこととして、新しいパラダイムの方向に、皆でたどり着く準備をしてきたのだなと思う。
信じられない数の人たちが新型コロナウイルスで命を落とし、全土封鎖・外出禁止令により経済的、社会的に脆弱な層にある人たちが抱える不安は大きくなる一方だ。健康リスク、社会不安が高まる中で、どうやって私たちは人間の営みを続けていくのか、「元に戻る」という選択肢をなくした、大きな岐路に人類全体で直面している。インドは何十年に一度の規模のサイクロンがこの2ヶ月で2つも発生し、北東部では大洪水が起きた。アメリカで始まった黒人差別撤廃を求める声は、今や世界各国でデモを引き起こしている。「今、何が起きようとしているのだろう」と問うてみると、「これまでのやり方ではないやり方にいきましょう」と地球が全力をあげて言っているような気がしてならない。もしそうだとするなら、反人身売買セクターは、これまでのやり方ではない、どんな可能性があるのだろうか。
今までやってきたことは大切だし間違っていなかった。それは否定されることではない。でも、ヒューマニティ(※1)として前に進むときに、加害者を訴求し、彼らを有罪判決にすることで、抑止力をあげていくというパラダイムはもはや通用しない、ということに私たちは気づいている。加害者の痛みとそうせざるを得なかった状況に本質的に手を入れるとするならば、何が悼まれる必要があり、誰がどうその「悼む」プロセスに参加することで、全員で前に進んでいくことができるのか、ということを考える局面にきたと思う。その意味において、私たちは新しい入口に立っている。
※1...人間としてのあたたかみをもった人類
自分自身の変化
今回の大型サイクロンで、トラフィッカー(女性たちをだまして売春宿に売る者)たちの家も流された。全土封鎖で人の動きが止まったことにより、彼らのビジネスはあがったりだ。そこにサイクロンでの被災が追い打ちをかけ、人身売買の新しいリクルーティングが始まっている。自分を相手取って裁判を起こしたサバイバーリーダーたちへの脅迫・嫌がらせもひどくなっている。中学生の女の子が集団レイプされ、子どもの虐待や幼児婚の事例が増えている。その状況の中で、「加害者にも痛みや背景がありますよね」なんて、とんでもないキレイごとだと思う。自分が人に売られたという経験を持たない以上、加害者を前にしたときの彼女たちの恐怖や痛みは計り知れない。だから、加害者への関わりを始めてパラダイムシフトを起こそうよ、というのは理想論にすぎず、その一歩を踏み出すのは無理だと強く思っていた。
昨年度の調査の一つに、トラフィッカー調査がある。かものはしがこれまで集めてきたデータを元に、429人のトラフィッカーの基礎情報(男女比、被害者との関係性等)と彼らを取り巻く捜査・裁判データを分析し、その結果を私はパートナー団体及びサバイバーリーダーたちに説明した。それを見たサバイバーリーダーたちの凍り付いた表情、あの場の張り詰めた空気感を、私はずっと忘れられない。この10年で有罪判決になった加害者は429人中3人しかおらず、10人は無罪、68人は保釈金を払って保釈され、うち26人は行方がわかっていない。10年たっても判決までたどり着いたのはたったの3%。「429人のトラフィッカー」という言葉を聞いたときの彼女たちの恐怖感。そしてこのデータは、今彼女たちが勇気を出して始めた裁判が10年後も継続している可能性が高いことを示唆している。彼女たちは、このデータを使って何かの行動につなげたいと言ったけれど、3ヶ月たっても、6ヶ月たっても、具体的な行動にほとんど結びついていないことは、彼女たちの強い恐怖心を表していると私は思う。
一昨年、私たちが2013年から応援していたサバイバーが殺されたとき、私はあまりのショックと自分たちがやってきたことの無力さ、その理不尽さに胸が押しつぶされた。1年くらいは、彼女を惨殺した旦那さんを理解することはできないと思ったし、彼がゆるされてしまったら、彼女は浮かばれないと頑なに信じていた。「Forgiveness」という単語が出てくるたびに、私の胸はえぐられ、涙しか出てこなかった。時間がたち、たくさんの人の支えで、私は「ゆるすとは一体何か?」と思えるくらいには回復した。そして「なぜ彼女は殺されなくてはならなかったのか」というところで思考が立ち止まると、「ゆるす」「癒す」という統合された世界にシフトすることが難しくなるということに気づいた。

©Siddhartha Hajra
「ゆるす」とは、
「癒す」とは
2020年5月末、日本で緊急事態宣言が解除になり子どもたちの学校が再開される、というときに、体が動かなくなった。いつもは気力でなんとか動かせるのに、今回はどうにもダメで、おとなしくベッドで過ごすことにした。そのとき、インド事業のアドバイザーとして関わってくださっている山梨県立大学の西澤哲先生が、目黒区で起きた児童虐待死事件の、加害者である父親の心理鑑定をしたという記事をたまたま目にした。それを見ていたら、すとんと腑に落ちた。5歳の子どもを死に追いやったそのこと自体は許されることではない。でもそこにいたるまでに、彼にも「子どもと幸せな良い家庭を築きたい」という夢があった。でも、子どもだから当然親の言うことを聞いてはくれず、どうして自分の言うことだけ聞いてくれないのかという無力感や被害者感が強くなっていく。それが増幅されると、力という暴力につながり、虐待はエスカレートしていく。これは、日常的に私たちにも起きていないだろうか。小さな息子が泣きじゃくるとき、私は一生懸命彼の涙をぬぐい、最善を尽くす。それでも彼が泣き止まずさらに泣き声を大きくし、周りの人がじろじろ見始めると、私だって泣きたくなる。もういい加減にしてよ、なんで分かってくれないのよ、と思ったことは一度や二度ではない。自分の中のその被害者感を補う手段として「力」を使うことが、私にも本当になかったと言えるだろうか?あの児童虐待死の、最後の事象だけを切り取って「あの人がいけなかった」と責めることにどれだけの意味があるのだろうか、と、西澤先生の記事を読みながら思った。今までの私たちの学びのなかで、トラフィッカーも元被害者であることが多いことがわかっている。そうだとすると、その被害者としての痛みが何か関係していて、人を売ることで、自分の持っている力を再認識をする行為が人身売買の裏側にあるのではないか。
かものはしを支え、かものはしとして、私たちとずっと歩んできてくれたループやウマ(※2)には、大きな痛みがある。現場で生じることの重さや、苦しいながらも前に進んできた彼らのレジリエンス、美しさがある。そんな彼らと、事業のビジョンを紡いでいく中で、自分たちのアイデンティティは何だろうか?という話をする。私たちは「healer(癒す人)」でありたいという夢を持っている。5年後、かものはしがインドで事業を完了し、インドから撤退する、そのときに、私たちのコレクティブアイデンティティ(※3)が「healer」だとするならば、担うべき役割は何か?撤退は、支援を受ける側にとって大きな痛みを伴うプロセスだ。どれだけ持続可能な事業を作っても、どんなに円満な別れ方でも、大なり小なりそこには痛みが伴う。かものはしから受け取る月次給付金が命綱のサバイバーリーダーからすればそれは尚更だ。3人でその「場所」からシステムに関わるとき、視点が変わり、事業の組み立て方が変わる。システムにある怒りや痛みや苦しみを増幅させるという役割から、今ここに欠けているものは何だろう、聞いてほしいと渇望している声はどんなものだろうというところに好奇心を向け、その声をファシリテートしていく役割へ。自分の中に同質の痛みがあるとき、他者の悲しみに自己が共鳴し動けなくなる。そこを突破して、パラダイムを動かすためには、自分たちがどうありたいのか、何のアイデンティティからそのシステムに関わるのかが大切な気がしている。そのリーダーシップを私たちが発揮するとき、それは人に「伝染」し、その人たちのエネルギーになっていくところを2019年はたくさん見た。何をどうゆるすのか、何をどう癒すのか。それはまだ私たちにも100%わかっていることではない。でも、次の5年、自分たちが歩みを向けたい方向だけは明確である。その先に、これまでとは違うやり方での人身売買問題の解決が、私たちが作りたい社会の姿があるような気がする。来年のこの時期までにどんな一年が過ぎていくのか、今から楽しみだ。
※2... かもインドチームメンバー ※3...グループとして有するアイデンティティ
※本サイト上の掲載情報の著作権は、本団体に帰属するものであり、本サイトの内容をかものはしプロジェクトの許可なく、複製、掲載することを禁止します。本サイトの内容を各種媒体へ転載する場合は、事前にご連絡ください。
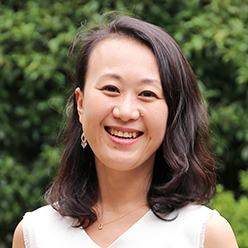
清水 友美Tomomi Shimizu
インド事業部ディレクター
2011年から2年間のインド駐在を経て、2013年7月からかものはし東京事務所勤務。大学院卒業後、国際機関や人道支援機関で開発援助事業に携わる。森と温泉が好き。




