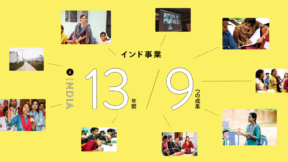31
インドの事業終了に
寄せて共同創業者・理事長の青木からのメッセージ
date2025.8.7
writer 青木 健太
青木 健太
[写真] 2025年4月のタイ・バンコクでの関係者会議にて。インド事業は、Toriiにバトンを渡す。
Toriiの清水(左)、Uma(中央左)、Roop(右)と青木。
「私はこの言葉を聞いたとき、
パソコンの前で不覚にも
泣いてしまいました。」
writer

青木 健太共同創業者・理事長
2002年、村田、本木とともにかものはしプロジェクトを創業しました。2018年にNPO法人SALASUSUを設立し、カンボジアで公教育改革に取り組んでいます。2022年からかものはしプロジェクトの理事長に就任しました。
事業終了という決断が
意味するもの
2012年から取り組んできたインド事業は、今、大きな転換点を迎えました。それは、かものはしにとっては事業に区切りをつけることであり、現地にとっては、これまで照らしていた太陽が西の空に沈んでいくような出来事かもしれません。しかし、長期的なインド社会の変化を考える中で、私たちができる最善の決断をしたと信じています。夕日が沈むと夜の静寂が訪れ、暗闇は生き物たちを包み込みます。その後、徐々に東の空が明るくなると、生き物は目覚め、命がいきいきと彩る新しい一日が始まります。インド事業にも、そんな日がやってくると信じています。
私たちは当初、カンボジアで培った経験をインドでも再現できると確信していたように思います。インド事業を通していくつもの成果を得られましたが、同時に、想像を超える複雑な現実にも直面しました。数え切れないほど多くの言語と文化、多様性、複雑な法律や行政、NGOや地域コミュニティなど、さまざまなステークホルダーとの高度な連携が求められました。こうした要素が絡み合う中、単純な支援モデルは通用しないことを痛感しました。それでも、長きにわたって事業を支えてくれたインド事業部のスタッフ、パートナー団体の方々から、ときには教わり、学び合いながら事業を継続することができました。

©Natsuki Yasuda
2015年のインド出張時に村でヒアリングをしている青木、本木、村田、清水。法執行を中心とした事業を行っていた。
だからこそ、事業終了の決断は簡単ではありませんでした。事業評価の実施を含む多くの議論と反省を経て、「かものはしとして最善を尽くすために必要な選択は何か」を問い続けました。人身売買の課題の深刻さや活動の持続可能性、本質的な成果を見つめ直しました。その結果、私たちはこの活動を次のステージへと進めるために、新たな道を選びました。
今回の決定にあたり、事業に関わるサバイバー(人身売買被害者)やパートナー団体など延べ21団体、約100人へ説明と意見交換を行いました。どんな反応が返ってくるか不安もある中で、あるサバイバーが言葉をかけてくれました。
「かものはしが日本も含めてさまざまな社会課題に挑戦していることに共感した。でもここで別れてしまうのはあまりにも寂しい。いつか国際会議で会える日を楽しみにしている。かものはしは日本代表として、私たちはインド代表として参加するから。」
私はこの言葉を聞いたとき、パソコンの前で不覚にも泣いてしまいました。壮絶な人生を乗り越え、仲間たちのことをケアしながらも、海の向こうの私たちを仲間として励ましてくれる。それだけの関係を築いてきたインド事業のスタッフ、彼女たちの回復とリーダーシップの発露に力を注ぎ続けたパートナー団体の努力と成果がふっと自分にふりかかって感じられる、そんな瞬間でした。
現場の困難さと
希望を感じた瞬間
インドの現場では、日々さまざまな困難に直面してきました。サバイバーが自らの苦しい過去や現状に直面し、精神的に追い詰められることも多く、その都度、緊急の支援が必要でした。スタッフも心身ともに消耗し、現場を維持すること自体が大きな挑戦でした。
めまぐるしく変わる現地の様子を把握するだけでも大きな苦労がありました。文化や切迫感の違いの中でぶつかることも多く、このまま事業を続けられるのだろうかと不安になることも何度もありました。
それでも私たちを支えてくれたのは、現場で起こる希望のある変化でした。
あるサバイバーは、過去のトラウマを乗り越え、自らのコミュニティでリーダーとして他の人々を励ましはじめました。自身の経験を活かし、地域に深く根ざした支援を自発的に展開するリーダーも現れました。一人ひとりの自分の人生を取り戻すどころか、仲間や地域のために尽くす姿は、私たちに勇気と希望を与えてくれました。

©Shirsendu Roy
サバイバーリーダーが自発的に活動を行う姿も見られるようになった。
私たち自身の痛みを伴う
変化と成長
インド事業を通じて、私たちはNGOとしての活動やあり方を根本から問い直す機会に恵まれたともいえます。
最初は「支援する側」として現地に入った私たちでしたが、現地メンバーやサバイバーとの深い対話を重ねるうちに、自分たちの考え方やアプローチが現地のリアリティに合っていないことに気付かされました。そうした経験の中で、私たちは「支援する側」ではなく、「ともに学ぶパートナー」としての関係性を築くことが重要だと理解しました。
とはいえ、それは「痛み」も伴いました。現地の仲間との激しい議論を通じ、知らず知らずのうちに押しつけていた支援の枠組みやエゴ、前提を一つひとつ解体していきました。それは同時に、私たち自身が人間の尊厳や真の支援のあり方について深く内省し、成長する大切な機会でした。
「どんな人生を送っていようと、一人ひとりの人が持っている尊厳を誰も奪うことはできないんだ。」
むしろ、当事者であるサバイバーリーダーが自分自身の意志で進んでいく姿を応援することこそ、私たちNGOのできる本当に意味のあることだということを学びました。言い換えれば、ある人たちを「被害者」としてラベリングすることの暴力性、人間観、真の意味での人間の公平さに気付けたことが大きな財産だったと思います。

©Siddhartha Hajra
サバイバーやパートナーNGOと深い対話を重ね、互いに学び合うことを大切に歩んできた。
Toriiへの期待と、
インドから世界へ広がる
ビジョン
今回の事業終了は単なる終わりではなく、新しい始まりです。その象徴が、新たに誕生したToriiという団体です。Toriiは、かものはしプロジェクトでのインド事業の経験を土台としつつ、その学びを東南アジア・他の南アジア及び日本で生かしていく中間支援のスタートアップとして立ち上がりました。その中で、かものはしが支援してきたインドの事業についても現地パートナーとともに着地させていくことを引き受けてくれました。彼らのアプローチは、コミュニティが主体となり、それに呼応する形で資金提供者の深い共感と変容を呼び起こし、持続可能な支援体制を築くことに重点を置いています。
かものはしとしても、一層複雑化するインドの社会の未来を考えたとき、現地に根ざして本質的な変化を追求し続ける最適なバトンの渡し先が「Torii」という結論を出すことができました。
Toriiの設立者である清水、Uma、Roopというインド事業をこれまで中心的に担ってきたメンバーは、現地の複雑な課題を熟知しており、現場の状況を敏感に捉えた革新的な支援を実現すると確信しています。インドにおける長期的な問題解決を考えたとき、これ以上ない方々にこのバトンを託し、未来を拓いてもらえることを本当に嬉しく、誇りに思います。

©Raj Sekhar
2024年4月にデリーで開催したリーダーシップネクスト事業の年次会議で話すRoop。
Toriiへとバトンを渡していく中で私の記憶に残っているのは、Toriiとしての夢を語ってもらった会議のことでした。かものはしが大事にしている尊厳や、それを現場、NGO、資金の出し手を一気通貫して大事にしていこうとする価値観、そしてその戦略を語ってくれたとき、「この人たちがいてくれればこのインドのエコシステムがもっと発展していくことができる」と安心したことを覚えています。
そして、かものはしプロジェクトも今後はインドで培った知見や学びを整理し、日本を含む世界の他地域でも活動を展開していきます。
私たちが得た経験は、決してインドだけに留まるものではないからです。
最後になりますが、これまでインド事業をあたたかく支えてくださった皆さまに心から感謝申し上げます。そして、新しい道を歩み始めたToriiへの引き続きのご支援と、かものはしプロジェクトの今後の活動にも、ぜひご注目いただければ幸いです。
ToriiのWEBサイトはこちらインド事業終了に関するこちらの記事も、合わせてお読みください。
(2024年度年次報告書から読むこともできます。)
date2025.8.7